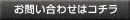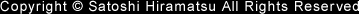上原博之師
「涙腺が弱いから…」
1月28日に行われたJRA賞授賞式の席で、調教師・上原博之はそう呟いた。JRA賞最優秀短距離馬を手土産に引退するダイワメジャー。彼とともに戦った四年半ほどの歳月は、上原の馬人生を何倍も濃密なものにした。
57年生まれの上原。高校時代、馬術の世界で彼の名は全国に轟いた。東日本大会で優勝。国体でも準優勝を果たした。
中央大学法学部に進学後も馬術は続けた。全日本学生選手権3位など、昂然と胸を張って馬を操った。
馬術界に上原有り。しかし、決して浮かれた気分にはなれなかった。狭い世界でのみ通じるコンセンサスに苛立つ日もあっただろう。その思いが「もっと一般社会に馬術を普及させたい」という願いとなり、その願いをかなえてくれそうな就職先を探すことになった。しかし、思うような職場はなかなかみつからない。JRAの受験にも失敗すると、もう一年、学生生活を続けることを決意した。これが、当時、本人が考えていた以上に、大きなターニングポイントとなるのだった。
五年目となった学生生活。イギリスとドイツで半年近く暮らした。イギリスでは馬術のプロを養成する学校へ通い、馬漬けの日々を謳歌した。そんなある日、デモンストレーションを行うため、馬とともに泊りがけの小旅行へ出掛けることになった。デモンストレーションの会場は、グッドウッド競馬場。上原と競馬との最初の出会いだった。
帰国し、学校を卒業した後は乗馬クラブに勤めた。その後、先輩の勧めもあり競馬の世界に足を踏み入れることとなった。調教助手時代も積極的にヨーロッパへ飛び、見聞を広めると、93年、当時としては異例の若さともいえる35歳で調教師免許を取得した。
調教師となって区切りの十年目。03年にダイワメジャーが入厩した。
「生まれてすぐに体はみさせてもらっていました。骨格がしっかりして、当時から垢抜けた肉体の持ち主でした」
しかし、みた目は獅子でも中身は猫のようだった。入厩後のメジャーはほんの少しの環境の変化に過敏に反応し、体調を崩した。皮膚が荒れ、腹を下した。デビュー戦ではそれをまともに表出。シクシクとする腹に耐えられなくなったのか、パドックで寝転んでしまった。
「能力的には相当のものを持っていることは分かっていた」だけに、上原の胃もキリキリと音を立てた。
もちろん、この状況にただ手をこまねいていたわけではない。上原はメジャーのために次から次へと弾を撃ち続けた。
まずは、何をみても何を聞いても動じない精神力を養うことから始めた。基本中の基本、時間をかけて歩く練習をした。運動時にはトレセンのありとあらゆる場所を歩かせ、様々な光景をみさせた。馬房内には有線放送を流し、音に対して過剰反応をしないように慣れさせた。競馬場ではスクーリングを行なうこともあった。もちろん、寝転ぼうとする素振りをみせた時は、叱りつけたし、パドックでは調教助手が跨って歩かせるなど、手を打った。
一進一退を繰り返す中で、皐月賞を勝ち、見込み通り高い能力の持ち主であることは証明してみせた。しかし…。
その後はノド鳴りに悩まされた。思い切ってメスを入れると、メジャーは鮮やかに復活した。
秋の天皇賞、安田記念、そしてマイルチャンピオンを2回制し、06年、07年と2年連続で最優秀短距離馬に選出された。
そればかりか、精神面の影響がまともに出ることの多い海外遠征でも3着に好走してみせた。07年のUAE、ドバイデューティーフリーでの出来事である。
「環境の変化などによる影響がモロに出る繊細なタイプなので、遠征に対する不安はあったけど、現地では皮膚炎が出ることも下痢になることもなかった」
日本航空にかけあい、輸送用のコンテナを事前に美浦へ運んでもらった。輸送する何日も前から幾度もそこへ積んでは降ろした。そうすることで、メジャーのコンテナに対する恐怖心を払拭した。往復の輸送をこともなげに行なえたことが、ドバイでの好走と無関係でないのは明らかだ。
07年12月23日、うっすらと雲に覆われた月が見え隠れする下、ダイワメジャーの引退式がおこなわれた。メジャーとともに山を越え、谷を渡った四年半を思い起こすと、上原の涙腺はコントロールを失い、眸から涙が溢れ出た。
「スピードもパワーもあったけど、ヤンチャで、繊細で、手がかかった。でも、レースでは良い走りをみせてくれた。自在性があって、距離もこなしてくれた。重賞を一つ勝つのだって大変なのにGⅠを五つも勝ってくれた。メジャーには本当に頭が上がりません。感謝しています」
GⅠを5回も勝てるような名馬はそうはいない。それほどの馬に巡り会う確率も決して高くはないだろう。しかし、この四年半の経験を糧に、「再びそういう馬を育てることがメジャーへの最大の恩返しになる」と、上原の潤んだ眸が語っていた。 (文中敬称略)(08年掲載)